中性子
| 中性子 | |
|---|---|
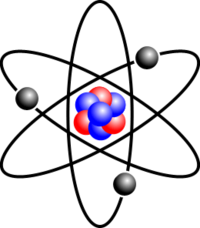 | |
| 組成 | udd |
| 粒子統計 | フェルミ粒子 |
| グループ | バリオン |
| 反粒子 | 反中性子(n) |
| 理論化 | アーネスト・ラザフォード (1920) |
| 発見 | ジェームズ・チャドウィック (1932) |
| 記号 | n |
| 質量 |
1.674927471(21)×10−27 kg[1] 939.5654133(58) MeV/c2[2] |
| 平均寿命 | 886.7±1.9 秒[3](核子や中性子星以外) |
| 崩壊粒子 | 陽子 |
| 電荷 | 0 |
| スピン | 1⁄2 |
| ストレンジネス | 0 |
| アイソスピン | −1⁄2 |
| 超電荷 | 1⁄2 |
| パリティ | +1 |
概要
編集中性子の発見は1920年のアーネスト・ラザフォードによる予想に始まり、その存在の実験的証明は1932年にケンブリッジ大学の物理学者ジェームズ・チャドウィックによってなされた[注 2]。その実験とは、ベリリウムに高速のα粒子を当てることで次の核反応
を起こし、ここで発生する粒子 n をパラフィンなどで受け、原子核と衝突させることでさらに陽子を飛び出させ、この荷電粒子である陽子を検出するというものであった[4]。チャドウィックは上記の核反応で発生する粒子(当時はまだベリリウム線と呼ばれていた)n が、陽子とほとんど同じ質量で中性(電荷を持たない)の新しい粒子からなる粒子線であることを確認し、これを中性子 (neutron) と名付けた[5]。
中性子は、電荷を持っていないことから[注 3]、他の電荷をもつ陽子などに比べて、入射した物質の原子核と容易に直接反応することができる。電磁気力の影響を受けない中性子線は透過性が高く、原子核の核変換に使う粒子として重要である[注 4]。
特徴
編集自由な中性子、及び中性子数過剰の原子核中の中性子は不安定でありベータ崩壊を起こす[注 5]。自由な中性子は平均寿命 886.7±1.9 秒(約15分)[3]、半減期約10.3分[6]で陽子と電子及び反電子ニュートリノに崩壊し、それを反応式で表すと
となる[注 6]。中性子はバリオンの一種であり、ヴァレンス・クォーク模型の見方をとれば、2個のダウンクォークと1個のアップクォークという3個のクォークによって構成されている[7]。中性子は全体として電荷を持たないが、内部では正負の電荷が分布しており、その広がりは約 10−16 m である[7]。
電荷を持たない中性子と原子との相互作用は、非常に短距離でのみ働く核力によるものがほぼ全てである[注 7]。また、核力の到達範囲はせいぜいπ中間子の換算コンプトン波長 h/2πmπc である約 1.4×10−15 m[8] - 2.0×10−15 m[6] 程度、即ち中性子の電荷分布の広がりである 0.1 fm[7] 程度しかない。従って、物質中を移動する自由な中性子は、原子核と「正面」衝突するまで直進する。原子核の断面積は非常に小さいため衝突は稀にしか起こらず、中性子は衝突までに長い行程を飛ぶことになる。生成した中性子が他の原子核と衝突するまで移動する距離を平均自由行程(英: mean freepath)という指標で表す[注 8]。
弾性衝突を起こすような場合、運動量保存則に従い、ビリヤードのボールが互いに衝突するように振る舞う。もし衝突された核が重い場合は核の加速は比較的少ない。中性子とほぼ等しい質量をもつ陽子(水素原子)と衝突した場合、陽子は元々の中性子が持っていた運動量のほとんどを受け取りはじき出される。一方、中性子はほとんどの運動量を失うが、この衝突の結果生じる二次的に放射された粒子が電荷を持っている場合、電離作用があるため、検知することが可能である。
電気的に中性であるため、観測だけでなく中性子を制御するのも難しい。荷電粒子に対しては電磁場によって加速、減速、軌道修正などの操作や制御が可能であるが、中性子にはそれが使えない。自由中性子を制御し、減速、進路の変更、吸収などの結果を得るには進路に原子核を配置するしかない。このことは平均自由行程と併せて原子炉や核兵器を設計する際、非常に重要である。
諸定数
編集中性子の質量などは、物理定数の1種としてCODATAより4年に1度のペースでNISTのWebページを介して公開されている[9]。
- 質量
- 中性子の質量 mn は
- であり[1][2]、統一原子質量単位で表すと 1.00866491588(49) u となる[10]。
- また、陽子の質量 mp や電子の質量 me に対する比は
- である[11][12]。
- さらに、中性子の質量 mn は同じ核子である陽子の質量 mp よりわずかに大きい程度で、その差はわずか
- である[13]。ただし、中性子は陽子とは異なり、電気的に無電荷(中性)であるため、陽子や電子が持っているような比電荷という値を持たない。
- コンプトン波長
- 中性子のコンプトン波長 λn や換算コンプトン波長 λn/2π は
- である[14][15]。
- 磁気モーメント
- 中性子は電気的には無電荷で中性であるが、磁気モーメントを持っており、その値 μn は
- である[16]。電気的には中性である中性子が磁気モーメントを持つ理由は、中性子を構成する3個の各クォークの磁気モーメントの和として説明される[8]。
- また、核磁子 μN に対する比(異常磁気モーメント)は
- である[17]。
中性子温度による分類
編集中性子はその運動エネルギー(運動速度)に応じて大体[注 9]以下のように分類される[18][6]。
| 中性子温度に応じた名称 | エネルギー (E) の範囲(電子ボルト) |
|---|---|
| 冷中性子 (cold neutrons) | E < 0.026 eV |
| 熱中性子 (thermal neutrons) | 0.001 < E < 0.01 eV |
| 熱外中性子 (epithermal neutrons) | 0.1 < E < 102 eV |
| 低速中性子 (slow neutrons) | 0.1 < E < 103 eV |
| 中速中性子 (intermediate neutrons) | 1 < E < 500 keV |
| 高速中性子 (fast neutrons) | 0.5 < E < 20 MeV |
| 超高速中性子 (ultrafast neutrons) | 20 MeV < E |
歴史
編集1914年にイギリスのラザフォードは、重い原子核ではα線を接近させてもクーロン力によって弾き返されるが、軽い原子核では原子核かα粒子いずれかの破壊が起こるのではないかと考え、1917年から1919年にかけて、さまざまな条件下で空気に対してα線を当て、ZnSのシンチレーションを利用して破壊の影響で生ずる可能性のある粒子を発見しようと試みた結果、水素の原子核が発見された[19]。この水素の原子核は、α線が空気中の窒素の原子核に当たった際に
という核反応によって生ずるものである。この結果を受けてラザフォードは、翌1920年にロンドン王立協会に於いて行なった講義の中で、原子核を構成する粒子には陽子の他に陽子とほとんど同じ質量で中性の粒子が存在すると予想した[20][21]。
1929年に中性子の発見により、ソ連のヴィクトル・アンバルツミャンとドミトリー・イワネンコは直ちに原子核の構造についての従来の見解を改変し、「原子核の中には中性子と陽子だけが含まれており、電子は存在しない」という説を提唱した。ヴェルナー・ハイゼンベルクもこれを支持し、以後の原子核理論の方向性を決めることになったと言われる彼の3部作の論文『原子核の構造について1〜3(Über den Bau der Atomkerne Ⅰ-Ⅲ)[22][23][24]』の基本仮定として採用されることとなった[25][7]。
それから10年後の1930年にドイツのW・ボーテとH・ベッカーは、ポロニウムから放出されるα線を、リチウム、ベリリウム、ホウ素などの軽元素に当てると非常に強い透過力をもった放射線(当時はまだベリリウム線と呼ばれていた)が放出されることを発見した[26][21]。2人はベリリウム線の正体はγ線であると推測し、そのエネルギーは普通のγ線の大体2倍程度であると結論付けた[27][21]。
その翌年の1931年に、ジョリオ=キュリー夫妻(イレーヌと夫のフレデリック)は、パリのラジウム研究所において、このベリリウム線をパラフィンやセロファンなどの水素を含む物質にあてると、これから高速度の水素核すなわち陽子が飛び出すことを発見した[28][21]。2人もやはりボーテとベッカーと同じくベリリウム線の正体はγ線であると考えていたが[29][7][21]、実験からさまざまな矛盾が出て来た[注 10]。その結果を受ける形で、同年、ケンブリッジ大学の Webster によって、ベリリウム線の放出がγ線の放出と全く異なることが示された。
これらの実験結果を総合して、同年に同じくケンブリッジ大学の物理学者ジェームズ・チャドウィックは、それら矛盾はベリリウム線をγ線と仮定していることに起因していることに気付き、これが陽子とほとんど同じ質量で中性(電荷を持たない)の新しい素粒子からなる粒子線であることを実験的に確認し[30][21]、これを中性子 (neutron) と名付けた[31][5][7]。
脚注
編集注釈
編集- ^ 陽子1個で出来ている 1
1 H と陽子3個で出来ている 3
3 Li の2つを例外として、2015年現在の時点で発見報告のある原子の内、最も重い 294
118 Og までの全ての"既知の"原子核は陽子と中性子の2種類の核子から構成されている。 - ^ チャドウィックによる実験的確証を得るまでの経緯については、チャドウィックによる中性子の発見が詳しい。
- ^ 電荷を持たないため、直接的に観測することが難しく、中性子の発見は電子や陽子と比べて遅れた。
- ^ 通常の状態では荷電していない原子は中性子と同じようには利用することができない。なぜならば、正電荷を持つ原子核の周りに負電荷を持つ電子が広く分布していることから、原子は中性子よりも約1万倍も大きいものとして扱わなくてはならないためである。
- ^ 例えば三重水素は重水素とは異なり、不安定核種である。
- ^ 同様な崩壊(β崩壊)が何種類かの原子核においても起こる。核内の粒子(核子)は、中性子と陽子の間の共鳴状態であり、中性子と陽子は互いにπ中間子を放出・吸収して移り変わっている。これは、アイソスピンという考え方に基づいたもので、陽子と中性子は質量や核力がほぼ等しいので、共にアイソスピンが ±1/2 の核子という1つの粒子の異なる荷電状態であり、+ の状態が陽子で − の状態が中性子であるとする考え方のことである。
- ^ 陽子、電子やα粒子などの荷電粒子や、γ線のような電磁波は、物質中を通過する際に電磁気力によって通過する物質の原子をイオン化するため、エネルギーを失う。イオン化に費やされたエネルギーはすなわち、荷電粒子の失ったエネルギーであり、その結果、荷電粒子は減速し、γ線は吸収されるが、中性子はそのような過程でエネルギーを失うことはない。
- ^ 空気中で 220 m、軽水の場合は 0.17 cm、重水では 1.54 cm、ウランでは 0.035 cm である。
- ^ 厳密な分類ではなく、ほぼその領域で分けられるという意味である。
- ^ 夫妻は陽子が飛び出して来る理由を、γ線が陽子に当たった際に発生するコンプトン効果であると考えた。そこで、飛び出して来る陽子のエネルギーからそのエネルギーを計算してみると、γ線の持つエネルギーが 50 MeV となった[21]。
出典
編集- ^ a b CODATA Value
- ^ a b CODATA Value
- ^ a b c 日本アイソトープ協会 (1992), p. 29.
- ^ Murray & 杉本 (1955), p. 29.
- ^ a b 武谷 (1954), pp. 93–95.
- ^ a b c 化学小事典
- ^ a b c d e f 日本大百科全書
- ^ a b 物理小事典
- ^ 2014CODATA推奨値(一覧)
- ^ CODATA Value
- ^ CODATA Value
- ^ CODATA Value
- ^ CODATA Value
- ^ CODATA Value
- ^ CODATA Value
- ^ CODATA Value
- ^ CODATA Value
- ^ 日本アイソトープ協会 (1992), pp. 29–30.
- ^ Rutherford (1919).
- ^ Rutherford (1920).
- ^ a b c d e f g チャドウィックによる中性子の発見
- ^ Ambartsumian1930 (1930).
- ^ Heisenberg (1932a).
- ^ Heisenberg (1932b).
- ^ 湯川, 坂田 & 武谷 (1965), pp. 44–45.
- ^ Bothe & Becker (1930a).
- ^ Bothe & Becker (1930b).
- ^ Curie (1931).
- ^ Curie & Joliot-Curie (1932).
- ^ Chadwick (1932a).
- ^ Chadwick (1932b).
関連文献
編集原論文
編集- アーネスト・ラザフォード
-
- Rutherford, E. (1919). “Collisions of alpha Particles with Light Atoms. IV. An Anomalous Effect in Nitrogen.”. F. R. S.. 6th series (The London, Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science) 37 (581).
- Rutherford, E. (June 3, 1920). “Bakerian Lecture: Nuclear Constitution of Atoms”. Proc. Roy. Soc. A 97 (686): 374-400. doi:10.1098/rspa.1920.0040.
- ヴァルター・ボーテおよびH.ベッカー
-
- Bothe, W.; Becker, H. (May 1930). “Künstliche Erregung von Kern-γ-Strahlen”. Zeitschrift für Physik A Hadrons and Nuclei (Springer-Verlag) 66 (5-6): 289-306. Bibcode: 1930ZPhy...66..289B. doi:10.1007/BF01390908. ISSN 0044-3328. OCLC 884174965.
- Bothe, W.; Becker, H. (May 1930). “Eine γ-Strahlung des Poloniums”. Zeitschrift für Physik A Hadrons and Nuclei (Springer-Verlag) 66 (5-6): 307-310. doi:10.1007/BF01390909. ISSN 0044-3328. OCLC 884174965.
- Becker, H.; Bothe, W. (July 1932). “Die in Bor und Beryllium erregten γ-Strahlen”. Zeitschrift für Physik (Springer-Verlag) 76 (7–8): 421-438. Bibcode: 1932ZPhy...76..421B. doi:10.1007/BF01336726. ISSN 0044-3328. OCLC 884174965.
- イレーヌ・ジョリオ=キュリーとフレデリック・ジョリオ=キュリーの夫妻
-
- Curie, I. (December 28, 1931). “Sur le rayonnement γ nucléaire excité dans le glucinium et dans le lithium par les rayons α du polonium.”. C. R. Acad. Sci. Paris 193: 1412-1414. ISSN 1631-073X. OCLC 49235124.
- Joliot-Curie, F. (December 28, 1931). “Sur l'excitation des rayons γ nucléaires du borepar les particules α Énergie quantique du rayonnement γ du polonium.”. C. R. Acad. Sci. Paris 193: 1415-1417. ISSN 1631-073X. OCLC 49235124.
- Curie, I.; Joliot-Curie, F. (April 11, 1932). “Émission de protons de grande vitesse par les substances hydrogénées sous l'influence des rayons γ très pénétrants.”. C. R. Acad. Sci. Paris 194: 273-275. ISSN 1631-073X. OCLC 49235124.
- Curie, I.; Joliot-Curie, F. (April 11, 1932). “Sur la nature du rayonnement pénétrant excité dans les noyaux légers par les particules α.”. C. R. Acad. Sci. Paris 194: 1229-1232. ISSN 1631-073X. OCLC 49235124.
- ジェームズ・チャドウィック
-
- Chadwick, James (February 27, 1932). “Possible Existence of a Neutron”. Nature 129 (3252): 312. Bibcode: 1932Natur.129Q.312C. doi:10.1038/129312a0. ISSN 0028-0836. OCLC 263593080.
- Chadwick, J. (May 10, 1932). “The Existence of a Neutron”. Proc. Roy. Soc., A (F.R.S.) 136 (830): 692-708. doi:10.1098/rspa.1932.0112.
- Chadwick, J. (June 27, 1933). “Bakerian Lecture. The Neutron”. Proc. Roy. Soc., A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 142 (846): 1-25. Bibcode: 1933RSPSA.142....1C. doi:10.1098/rspa.1933.0152.
- ヴェルナー・ハイゼンベルク
-
- Heisenberg, W. (January 1932). “Über den Bau der Atomkerne. I [原子核の構造について 1]”. Zeitschrift für Physik A Hadrons and Nuclei (Springer-Verlag) 77 (1-2): 1–11. Bibcode: 1932ZPhy...77....1H. doi:10.1007/BF01342433. ISSN 0044-3328. OCLC 884174965.
- Heisenberg, W. (March 1932). “Über den Bau der Atomkerne. II [原子核の構造について 2]”. Zeitschrift für Physik A Hadrons and Nuclei (Springer-Verlag) 78 (3–4): 156–164. Bibcode: 1932ZPhy...78..156H. doi:10.1007/BF01337585. ISSN 0044-3328. OCLC 884174965.
- Heisenberg, W. (September 1933). “Über den Bau der Atomkerne. III [原子核の構造について 3]”. Zeitschrift für Physik A Hadrons and Nuclei (Springer-Verlag) 80 (9–10): 587–596. Bibcode: 1933ZPhy...80..587H. doi:10.1007/BF01335696. ISSN 0044-3328. OCLC 884174965.
- ヴィクトル・アンバルツミャン
-
- Ambarzumian V., Iwanenko D. (1930). Les électrons inobservables et les rayons. Paris: Compt. Rend. Acad. Sci. Paris. pp. 582.
- “[Astrophysics]” V. A. Ambartsumian — a life in science. 51. London: Springer. (2008). pp. 280—293. doi:10.1007/s10511-008-9016-6.
参考文献
編集書籍
編集- 洋書
-
- Profio, A. Edward (February 3, 1976). Experimental Reactor Physics (1st ed.). New York: John Wiley & Sons. p. 4. ASIN 0471700959. ISBN 0-471-70095-9. NCID BA07529299. OCLC 1849155
- 和書
-
- スティーブン・ワインバーグ 著、本間三郎 訳『電子と原子核の発見―20世紀物理学を築いた人々』日経サイエンス社、1986年1月23日、171-178頁。ASIN 4532062608。ISBN 978-4532062606。 NCID BN00244226。OCLC 674589858。全国書誌番号:86023308。
- エミリオ・セグレ 著、久保亮五、矢崎裕二 訳『X線からクオークまで―20世紀の物理学者たち』みすず書房、1982年12月24日、235-245頁。ASIN 4622024667。ISBN 978-4622024668。 NCID BN00625139。OCLC 674354038。全国書誌番号:83015277。
- ノーベル財団 著、中村誠太郎、小沼通二編 編『ノーベル賞講演、物理学』 第5巻、講談社、1978年10月、141-152頁。ASIN 4061263358。ISBN 978-4061263352。
- ジェームズ・チャドウィック 著、木村一治、玉木英彦 訳『中性子の発見と研究』大日本出版、1950年、3-66頁。ASIN B000JB7JHW。
- 日本アイソトープ協会(編) 編『放射線・アイソトープ 講義と実習』丸善、1992年10月。ASIN 4621037455。ISBN 978-4621037454。 NCID BN08081205。OCLC 674781852。全国書誌番号:93002007。
- Murray, Raymond L. 著、杉本 朝雄 訳『原子核工学』丸善、1955年。ASIN B000JB4RX6。
- 湯川, 秀樹、坂田, 昌一、武谷, 三男『素粒子の探求』勁草書房〈科学論・技術論双書〉、1965年5月。ASIN 4326798033。ISBN 978-4326798032。
- 原島, 鮮『熱力学・統計力学』(改訂版)培風館、1978年9月。ASIN 4563021393。ISBN 978-4563021399。 NCID BN00073393。全国書誌番号:78030419。
- 武谷, 三男『弁証法の諸問題』勁草書房・理論社、1954年11月20日。ASIN B000JB5HKI。
- 『物理小事典』(第4版)三省堂、2008年(原著1994年4月)。ASIN 4385240167。ISBN 978-4385240169。 NCID BN10774805。OCLC 675375379。全国書誌番号:94041161。
- 『化学小事典』(第4版)三省堂、2008年(原著1993年12月)。ASIN 4385240256。ISBN 978-4385240251。 NCID BN10357874。OCLC 674607619。全国書誌番号:95021622。
関連項目
編集外部リンク
編集- “Fundamental Physical Constants — Atomic and Nuclear Constants” (PDF). NIST (2015年6月25日). 2015年6月28日閲覧。
- “CODTA Value: neutron mass”. NIST (2015年6月25日). 2015年6月28日閲覧。
- “CODATA Value: neutron mass energy equivalent in MeV”. NIST (2015年6月25日). 2015年6月28日閲覧。
- “CODATA Value: neutron mass in u”. NIST (2015年6月25日). 2015年6月28日閲覧。
- “CODATA Value: neutron-electron mass ratio”. NIST (2015年6月25日). 2015年6月28日閲覧。
- “CODATA Value: neutron-proton mass ratio”. NIST (2015年6月25日). 2015年6月28日閲覧。
- “CODATA Value: neutron-proton mass difference”. NIST (2015年6月25日). 2015年6月28日閲覧。
- “CODATA Value: neutron Compton wavelength”. NIST (2015年6月25日). 2015年6月28日閲覧。
- “CODATA Value: neutron Compton wavelength over 2 pi”. NIST (2015年6月25日). 2015年6月28日閲覧。
- “CODATA Value: neutron magnetic moment”. NIST (2015年6月25日). 2015年6月28日閲覧。
- “CODATA Value: neutron magnetic moment to nuclear magneton ratio”. NIST (2015年6月25日). 2015年6月28日閲覧。
- “チャドウィックによる中性子の発見”. 原子力百科事典 ATOMICA. 一般財団法人 高度情報科学技術研究機構 (RIST) (1998年5月). 2015年8月8日閲覧。
- 日本中性子科学会
- 日本大百科全書(ニッポニカ)『中性子』 - コトバンク